こんにちは!日替わりラジオ 火曜日 青山紀子です!
今日は、季節の変わり目、体の不調の話を。。。
ここ一週間、疲労感と眠気と微熱で、お風呂にはいっても寒気がするという状態で。。。


今、微熱のインフルエンザB型も流行っているらしく・・・。
結局、血液検査、尿検査、インフルエンザ、レントゲン、などやりましたが、異常はなく、
いつものように点滴をして、復活しました!

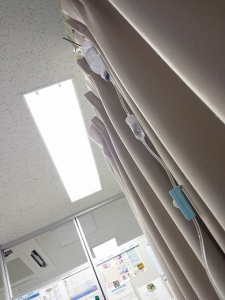
不調の時は、 「よもぎ蒸しがいいんじゃない?」と、友人にすすめられ、行って来ました!
韓国ではやったことあったけど、日本であったかな???
よもぎとハーブを煎じた蒸気を体にあてる民間療法。。。
この穴の下から熱い蒸気が出ます。マントをかぶって、汗をたくさんかきます。
サウナみたいな感じですかね。。。
粘膜から蒸気を吸収するので、皮膚から取り入れるよりも 42倍なんですって。
次第にマントを頭からかぶって、目も口も鼻からも蒸気を入れます。。。
たしかに、終わった後は体が軽くなったような・・・、でも唯一ひざだけが温まらない。。。
ひざの裏のリンパが詰まってる???(笑)
不調探しのたびは続く・・・。

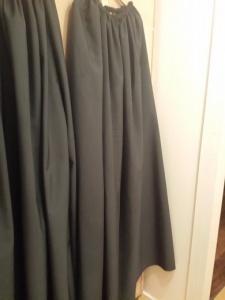
「紀子のオトナのたしなみ」
今日は、来週の「端午の節句 こどもの日」について。。。
柏餅やチマキを食べますが、一体なんで???
鎧兜や鯉のぼりはどんな意味が???
遠い昔に聞いたような気もするけど、はっきりはわからない あれこれをお届けしました。

◆端午の節句というのは、「端」(はじめ)の「午」(うま)の日をさしたのですが、
「午」(ご)の音が「五」に似ているので次第に、毎月5日を示すようになり、
奇数が重なることをおめでたいこととする 日本古来の考え方と相まって、
5月5日が端午の節句になったとのこと。
5月はもともと物忌みの月で、菖蒲やよもぎを軒下に飾り、邪気をはらう日だったのですが、江戸時代に男の子の節句に。。。
◆鎧やかぶとを飾るのは、武家社会からの風習。
身の安全を守るために神社におまいりするときに鎧兜を奉納したりもしていたようで、
自分の身を守る大切な宝物の意味合いもあるのです。
◆鯉のぼりは、町人階層から生まれた飾り。
鯉は、清流でも池でも沼でも生息できる生命力の強い魚。
また、「登竜門」の言葉の語源になった中国の伝説もあります。
黄河の激流が重なる難所を「竜門」といい、そこを唯一 下流から登ることが出来、
竜になる事が出来た魚が 鯉だけだったそう。
そのため、子どもが どんな環境にも耐え、立派な大人になれるようにとの
願いがこめられています。
◆菖蒲は、昔から薬草として使用され、悪月の5月に邪気を払うため、軒下にさしました。
その他、お酒に浸して菖蒲酒にしたり、枕の下に敷いて菖蒲枕にしたり、
お湯の中に入れて、菖蒲湯にしたり。。。
音が似ているので、武道を尊ぶ「尚武の節句」とも。
◆チマキは、古代中国では「忠誠心の象徴」
柏餅は、冬になっても落葉せず、新芽がでるとようやく落葉するため、
跡継ぎができるまで、親葉がおちないので、
家系が耐えないという 縁起担ぎから 来ているんですって。
また、神事にはお餅が欠かせないので、お餅を柏餅の葉で包むようになったそう。。。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
エンディングは、ボートレースラジオガールズとしてのお仕事のお話を。。。
G1トコタンキング決定戦 優勝者に 金メダル入り盾の授与に行きました!
(左)文化放送 野口逢里さん (右)KBS京都 海平和アナウンサーと。
詳しくは、こちらに ↓↓↓
とこなめに美女たちと〜トコタンキング決定戦 優勝戦〜
ボートレースのオフィシャルページでもボートレースラジオガールズのブログで
紹介されてますので、是非 ご覧ください ↓↓↓
ボートレースオフィシャル 東海ラジオ
「とこなめに美女たちと〜トコタンキング決定戦 優勝戦〜」

